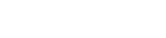江戸を立つ時、師である佐藤一斎から「盡己」(わが誠をつくす)の大書を贈られた方谷は、誠意こそ学問や行動の基になることを心に刻みました。藩主板倉勝職について帰る途中、その学識・人物を認められ、翌月には有終館の学頭(校長)に任命されました。時に32歳、六十石と御前町に邸宅をいただき、学問研究と藩士教育に邁進していきました。
有終館は初代板倉勝澄が延享3(1746)年に藩士のための学問所として置いたことに始まり、四代勝政の寛政10(1798)年頃に藩校として整備され、有終館と命名され、教育組織も整えられました。内山下にあった校舎が焼失した時は、奥田楽山学頭の努力で、通学に便利な中之町(現高梁幼稚園)に再建され、藩がなくなるまでこの場所で続きました。
藩校では朱子学を教え、藩士の子弟は六、七歳になると入学し、句読師(助教諭)より四書・五経の素読を受けます。素読は一人ずつ進度に合わせて音読し、覚えます。素読ができると会頭(教授)より論語、孟子などの講義を受けます。学頭は句読師や会頭を教えます。学問が進んだ人には歴史書( 資治通鑑、十八史略、日本外史)や詩文(唐宋八大家文や唐宋の詩)を教え、文章や詩をつくることを指導しました。
武術では剣、槍、弓など流派ごとに師範の指導があり、上達すると免許が出ました。
方谷にとって、この時が学問に専念できる良い時代でした。34歳の元旦に作られた漢詩を、山田琢氏訳でみると
『藩庁での賀宴もおわり私邸に坐している 書斎の窓辺で学業を始めよう 元旦の詩はもうできたし 去年の読みのこしの書物を開こう 農耕に代わる俸禄で飢えることなく 世俗と離れた役目で部屋は静かだ もし生涯をこのままで送れたら 必ずしも遠く世を避けるに及ばない』
この詩を作った天保9(1838)年に、方谷は師達の薦めで、自宅に家塾も開いています。臥牛山の麓にあったので「牛麓舎」と呼ばれました。その当時は武芸を重視し、学問を軽くみる風潮があり、塾生が書物を携えて往来すれば悪口、暴行されるので、それを懐に隠して往来する状態でしたが、京都の寺島白鹿師の息子義一や倉敷の三島中洲、川面の進鴻渓、藩士のなかで意欲に燃えた大石隼雄など、常に数十名が学んでいます。藩士や進、三島などはのちに藩政改革で大いに活躍しています。
牛麓舎の理念として立志・励行・遊芸の三条が示され、まず学問研修の志を立て、熱心に学習に励み、人格を磨き、その教養で詩文を作り楽しむことを目指しています。
塾での生活は、狭い部屋で多くの人が学ぶので、規則として、学問に専念し怠けない、人を見下げず自分を誇らない、起床と就寝時間を守る、節度を持って出入りする、勝手に飲食しない、無駄話をしないと決め、守れない人には、一、二度は注意するが更に違反したらすぐ退塾願を出すことが決まりで、塾生は熱心に自分で学習して、方谷の教えを受けました。
ある日、勉強家の進鴻渓が口から血を吐いたのに本を手放さなかったので、心配した塾生たちが方谷に、「勉強をやめさせて下さい」と訴えました。ところが方谷は彼の様子を見て、「勉強しておれば治る」と言ってみんなの動揺を抑えました。暫くすると元気になったそうで、彼は生徒一人ひとりを実によく理解し、誠意をもって指導しました。
天保10(1839)年の大火事で再び有終館が焼失した時、方谷は学業再開を急務と考え、藩校の五か年間の経費を前払いして、仮校舎の再建を急ぐよう懇願しました。その結果、素読の声が聞こえるようになり、街に活気が戻りました。
(文・児玉享さん)