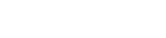○財政用語解説
財政用語は専門的かつ複雑ですが,その中で代表的なものを五十音順に解説しました。
◇依存財源:
市の意思によらず国・県の意思により定められた額を交付されたり,割り当てられたりする収入をいい,地方交付税,国庫支出金,県支出金,地方譲与税等がこれに該当します。
◇一般財源:
財源の使途が特定されず,どのような経費にも使用することができるものをいい,地方税,地方譲与税,地方交付税などがこれに当たります。これに対して,国庫支出金,都道府県支出金,地方債,分担金,負担金など財源の使途が特定されているものを特定財源といいます。
◇合併特例債:
市が発行する市債の1つであり,合併市町村が策定する新市建設計画に基づいて実施する公共施設の整備や合併後の地域振興のための基金の積立事業に対して発行が許可される起債です。合併特例債は元利償還時に償還額の70%が交付税により補填される有利な起債ですが,30%は高梁市において返済することなり発行は慎重に行われなければなりません。
◇過疎債:
市が発行する市債の1つであり,過疎地域に指定された市町村が策定する過疎計画に基づいて行う事業に対して発行が許可される起債です。過疎債は元利償還時に償還額の70%が交付税により補填される有利な起債ですが,高梁市においては未償還元金のもっとも多い起債となっています。
◇基金:
特定の目的のために財産を維持し,資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産で,条例により設置することができ,例えば福祉基金のように基金の運用による収入を各種の社会福祉事業に充てるなど,設置目的に基づき活用を図っています。
また,財政調整基金は,予期しない収入減少や支出増加といった,年度間の財源の不均衡を調整し,長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために設置しています。
◇基準財政収入額:
地方自治体が標準的に収入し得ると考えられる地方税等のうち,基準財政需要額に対応する部分で,標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち,都道府県にあっては80%,市町村にあっては75%の額とされています。(この残りの20%又は25%は,各地方自治体の独自施策の実施のために留保されているものです。)
◇基準財政需要額:
各地方公共団体が実際に支出した額あるいは支出しようとする額を算定するものではなく,地方自治体が合理的かつ妥当な平均的水準で行政を行った場合に要する財政需要を一定の合理的な方法で算出した額をいいます。
◇義務的経費:
性質別経費のうち義務的・非弾力的性格の強い経費で,一般には人件費,扶助費及び公債費を指します。人件費は経常的に支出を予定せざるを得ないし,扶助費は生活扶助をはじめ法令の規定によって支出が義務づけられており,また,公債費は負債の償還に要する経費であって,いずれも任意に節減できない経費です。
義務的経費の増加傾向は財政構造の硬直化を招く恐れがあるので,その内容,動向に注意する必要があります。
◇繰出金:
国民健康保険,基金等の特別会計,病院,水道,公共下水道の公営企業会計に対し支出される経費で,内容的には,公共下水道等にかかる投資的なもの,国民健康保険会計等に対する財政支援的なもの,基金会計に対する積立金的なものなどがあります。
◇経常収支比率:
人件費,扶助費,公債費等の義務的性格の経常経費に,地方税,地方交付税,地方譲与税を中心とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当されているかを見ることにより,地方自治体の財政構造の弾力性を判断するための指標として用いられているものです。
これが大きくなるほど,新たな財政需要に対応できる余地が少なくなり,一般的には,都市にあっては75%,町村にあっては70%程度が妥当で,これが各々+5%を超えると,その地方自治体の財政は弾力性を失いつつあると言われています。
◇公債費:
公債費とは市債の元金の償還及び利子の支払いに要する経費です。市債は,ある程度活用すべきですが,後年度の財政負担となります。このため,公債費の一般財源に占める割合を算出し,その限度を計数的に見ることとしており,この割合が一定割合を超えると,市債の発行が制限されることになります。
また,公債費は,消費的経費のうちの人件費及び扶助費とともに,義務的経費と呼ばれ,その増嵩は財政硬直化の要因となるため,留意が必要です。
◇公債費比率,起債制限比率:
いずれも,公債費(市債の元利償還金)の負担の程度を,「公債費に充当される一般財源」の「一般財源」全体に占める割合で示すもので,通常,財政の健全性がおびやかされないためには,公債費比率が10%を超えないことが望ましいとされています。
また,起債制限比率については,これが15%を超えると危険な水準となり,20%以上になると地方債の発行に制限を受けることとなります。
◇国庫委託金:
本来は国が行うべき事務を,国民の利便,経費の効率化等の観点から地方自治体に委託する場合,その経費の全額を国が地方自治体に交付するものです。
具体例としては,国会議員の選挙,国勢調査,外国人登録等があります。
◇国庫負担金:
地方自治体又はその機関が行う事務のうち,国が地方自治体と共同責任又は共通の利害関係がある事務に対して,経費の負担区分を定めて国が義務的に負担する金銭給付をいいます。
具体例としては,義務教育費国庫負担金,生活保護費国庫負担金,道路・河川・港湾等新設・改良費国庫負担金,災害救助事業費国庫負担金などがあります。なお,三位一体改革により本来の補助金削減ではなく負担金の廃止・縮減が多く行われています。
◇国庫補助金:
地方自治体が行う事務で,国がその実施を奨励するため,又は財政上特別な必要がある場合で国が必要と認めたときに支出されるものです。 補助対象事業は多岐にわたりますが,主には地方自治体が行う建設事業に対する補助金などがあります。
◇財政調整基金:
年度間の財源の不均衡を調整するための基金で,長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために,財源に余裕のある年度に積立てを行い,財源不足が生じる年度に活用するためのものです。また,各年度において決算上剰余金を生じたときは,その全部又は一部を積み立てることとなっています。
◇財政力指数:
地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいい,地方自治体の財政力を示す指数として用いられています。
◇債務負担行為:
将来にわたって支出が義務付けられる経費であり、公債費に準じて取り扱われることからも債務負担行為を設定するには議会の議決が必要です。具体例としては土地改良事業借入金元利補給などがあります。
◇三位一体改革:
地方分権の実現のために国と地方の役割を根本から見直した上で地方に更なる権限を移譲するとともに,地方の裁量が広がるように国庫補助・負担金の廃止・縮減を行い,地方の事務量に見合った税源の移譲を行うものです。このような改革を通じ地方交付税の見直しも同時に行っていくというものです。
しかし,現在進められている三位一体改革は,国庫補助負担金の削減に見合った税源の移譲がなされず,国に権限を残したままの交付金化や単なる補助・負担金の削減スリム化に終わっており,地方の裁量の拡大や財源の充実が不十分なままとなっています。
◇市債:
市債とは市が行う建設事業等の資金調達の手段として県の同意を受けて将来にわたり負担する債務のことです。 代表的なものに過疎債,義務教債,公営住宅債,合併特例債などがあります。一般家庭に例えると住宅建設のために借り入れる住宅ローンと同様のものです。
◇自主財源:
地方自治体が自主的に収入し得る財源をいい,地方税,分担金及び負担金,使用料及び手数料,財産収入,寄付金,繰入金,繰越金等がこれに該当します。
◇実質収支・単年度収支:
実質収支は,一会計年度の決算において,収支が赤字であったか黒字となっているかをみるための指標で,当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差引いた額から,翌年度へ繰り越すべき財源を控除して算出します。これは,本来当該年度に属すべき支出及び収入が,当該年度に実際に執行されたものとみなすことにより,実質的な収支の状況を見ようとするものです。
実質収支には,当該年度以前の財政運営の結果として累積された赤字や黒字の要素が含まれています。そこで,当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引き,当該年度一年だけの収支を表したものを単年度収支といいます。
◇実質収支比率:
標準財政規模に対する実質収支額の割合で示され,団体の財政規模やその年度の景況などによって一概には言えませんが,経験的には3%~5%程度が望ましいと考えられています。
◇消費的経費:
人件費,扶助費,物件費,維持補修費,負担金補助及び交付金等で,その経費の支出効果がその年度限り又は極めて短期間に終わるものをいい,後年度に形を残さない性質の経費です。
◇地方交付税:
地方自治体間の財源の不均衡を是正し,すべての地方自治体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必要な財源を保障するもので,国税のうち,所得税,酒税の収入見込額の32%と法人税の収入見込額の35.8%,消費税の収入見込額の29.5%,たばこ税の収入見込額の25%を合算した額に前年度以前の年度分の精算額を加減した額を総額とし,その94%が普通交付税,6 %が特別交付税として各地方自治体に交付されます。
普通交付税は,基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に,その超える額を財源不足額として交付されるものであり,一方,特別交付税は,特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものです。
◇投資的経費:
経費支出の効果が,施設等のストックとして後年度に及ぶ性質の経費で,普通建設事業費,災害復旧事業費があり,この割合が高いほど財政構造に弾力性があるといわれています。
◇特定財源:
財源の使途が特定されているものを特定財源といいます。
特定財源に分類されるものとしては,国庫支出金,県支出金,地方債,分担金,負担金,使用料,手数料,寄付金のうち使途が指定されているもの等です。
◇標準財政規模:
地方交付税算定時に基準財政収入額を元に求められる標準税収入額に、地方譲与税、交通安全対策特別交付金、普通地方交付税を加えたもので、 地方公共団体の標準的な一般財源の収入額を表します。起債制限比率などの財政分析数値に用いられます。
◇普通会計:
各地方自治体の財政状況の把握,地方自治体間の財政比較等のために用いられる統計上,観念上の会計を指します。
地方自冶体における会計は,一般会計及び特定の場合に設置される特別会計によって構成されていますが,個々の地方自治体ごとで各会計の範囲が異なっていることなどから,財政比較等においては,この普通会計を用いています。具体的には,一般会計と特別会計(公営企業会計など特定の特別会計を除く。)を合算し,会計間の重複等を控除したものです。